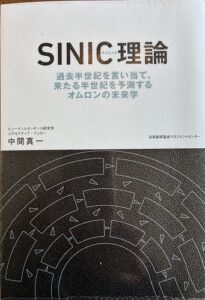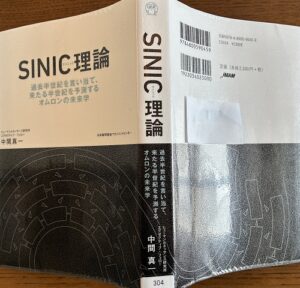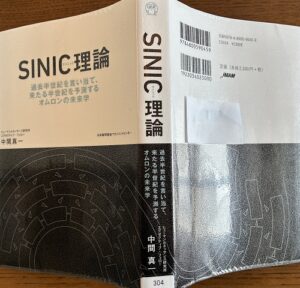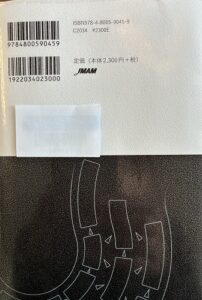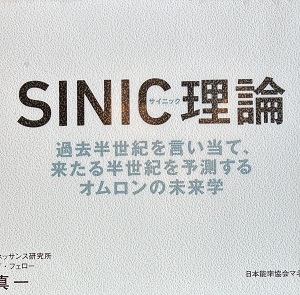Hiro
中間真一さんが書かれた『SINIC理論』を読んで,私なりに学んだことをこのレポートにまとめました。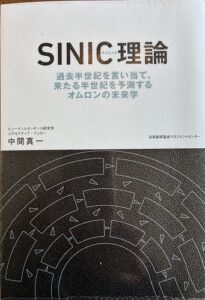

Hiro
中間さんの『SINIC理論』の内容をどの程度あなたに伝えられるのか今の私にはかわかりません。詳しく『SINIC理論』を知りたい方は,本書を読まれることをお勧めします。

Hiro
私は,今の時代が情報社会に向けての過渡期であり,それこそ『第三の波』(アルビン・トフラー著)に書かれている世界が訪れるだろうと考えていました。また,レイ・カーツワイル氏が予想している2045年前後に「シンギュラリティ」が来るかもしれません。あるいは,ユヴァル・ノア・ハラリ氏が『ホモ・デウス』で予想するように,ほんの一部の人間やAIが支配する世界が訪れるかもしれません。

Hiro
いろいろな本を読むと,この世界は情報社会になるだろうということは簡単に予想できました。

Hiro
ところが,この中間真一著『SINIC理論』を読むと,情報社会ではなく,世界は自律社会から自然(じねん)社会になるというのです。それも若い人が希望と情熱を持ってこの社会を変革していくだろうと予想しています。

Hiro
15世紀頃ヨーロッパにルネッサンスが訪れたように,これから第二のルネッサンスが来るだろうというのです。この新しい未来の考え方をあなたに伝えられたら,と思います。いつものように2,3の問題を解いていただきながらこの本の内容に迫っていきたいと思います。

Hiro
あなたは,<SINIC理論>を知っていますか?
本書のはじめに<SINIC理論>について説明がありますので,書き出してみます。
SINIC(サイニック)理論は,100万年前の人類の始原から歴史をたどり,そこから導かれる社会進化の理論から,さらに未来を展望する壮大な未来社会の予測理論です。だからこそ,この理論に基づいた未来シナリオは,決して,いたずらに悲観的な未来でもなく,無責任に楽観的な未来でもありません。大きな変化に遭遇するたびに,それを乗り越え,適応して,新しい社会を自ら創ってきた人間の力の可能性,そして未来への可能性を信じられるからこそ成り立つ,ありたいシナリオであり,あり得るシナリオです。
その未来シナリオは,確実に顕れ始めています。「情報化社会」を経て,「最適化社会」という極めて大きなパラダイム・シフトが,まさに足下で進み始めています。世界はこれをYUCAの時代などと呼びますが,そうではありません。渾沌の中からも,その先の光を見失わずに未来を拓くことができるのです。そのための羅針盤こそ,SINIC理論なのです。

Hiro
問題1.この頃日本では「不良老人」問題がニュースになったりしています。例えば,お店で自分の思いが通用しないときに老人が暴言を吐いたり,暴力をふるったりすることです。老人がこんなことを言ったりしたりするのは,なぜでしょうか。この本ではどうとらえているでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。
予 想
ア.人間は歳をとると我がままになってくるから
イ.人間は歳をとると理性的な判断ができにくくなるから
ウ.社会が最適化社会へと変化しているのに,老人は真の変容ができないままだから
エ.その他
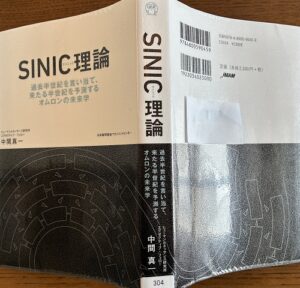

Hiro
正解は,ウ.社会が最適化社会へと変化しているのに,老人は真の変容ができないままだから,です。

Hiro
本書では,<自律難民としての「不良老人」問題>というタイトルで不良老人が出てくる理由を次のように書いています。
数年前,ロンドン・ビジネススクールの人材論の権威であるリンダ・グラットン教授らの『ライフシフト』(東洋経済新報社)という書籍が話題になった。この本では,人生100年時代の到来は,これまでのように,人生前半で教育を受け,仕事に従事し,引退するという,単線的な1つの人生ステージを前提とするのではなく,複線的でマルチ・ステージの生き方が必要となるということが主張されている。
そのためには,自律的に自らの人生を通じて,スキル,健康,人間関係といった「見えない資産」を育み,生涯を通じて自らの「変身」を続けていく生き方が重要になる。自分らしい生き方を,自分自身で描き,自ら実現を進めていくという自立と自律の生き方の勧めであった。
しかし,最適化社会の時代というのは,日本では団塊の世代,世界的にもベビーブーマー世代という大きな世代集団が,当然ならが一気に高齢期に入る時代である。ちょうど,日本では団塊の世代という大集団が,75歳以上の後期高齢者となる時期をとらえて,「2025年問題」と名づけられているが,この時期は,SINIC理論における自律社会の入口に立つ年と一致しているのも暗示的である。
彼らは,まさに戦後高度成長社会の中で,単線的なライフコース上をひた走り,成長至上主義の経済的豊かさを獲得して駆け上がってきた人々であり,走り終えた後の余生が幸せの高齢期であることを信じて疑わずに生きてきた世代である。
このように,昭和世代のほとんどが仕事から離れたものの,その後の自らの暮らし向きについて「こんなはずではなかった」と感じて,不良化してしまうのは,自律社会へと進む上での大きな障害となると予想される。もはや,高齢期が「余生」でなくなっている。高齢者の経験知を活かせることは最大限に価値として活かせるようにし,経験的な習慣が自立や自律の障害になる点については,社会としても支える仕組みを設け,社会のお荷物となる「不良老人」を生まないようにすることも,これから創るべき重要な兆しの1つとなるだろう。

Hiro
ここでSINIC理論の未来ダイアグラムを表してみます。
BC100万年 原始社会
→ BC1.2万年 集住社会
→ BC700年~ 農業社会
→ 1302年~ 手工業社会
→ 1765年~ 工業化社会
→ 1876年~ 機械化社会
→ 1945年~ 自動化社会
→ 1974年~ 情報化社会
→ 2005年~ 最適化社会
→ 2025年~ 自律社会
→ 2033年~ 自然社会

Hiro
今は2025年現在ですから,SINIC理論では自律社会※が始まるとなっています。私は,今の社会が自律社会とはどうしても思えません。あなたは,どう思いますか?
言葉の意味: 自律社会※とは、人々が社会や組織からのコントロールを必要とせず、自立した個が相互に支えあう社会を指します。
質問:あなたは,今(2025年現在)の社会は自律社会だと思いますか。次の選択肢から一つ選んで,その理由を考えてみてください。
予 想
ア.今の社会は自律社会だと思う
イ.今の社会は自律社会だと思わない
ウ.その他(あなたの考え)
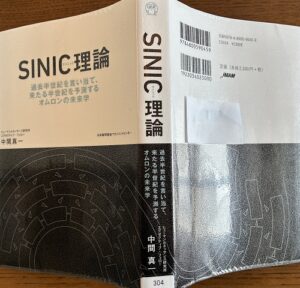

Hiro
自律社会では、個の心とそのつながりにより、新しいものが創造されることが期待されています。また、SNSにおける承認欲求の高まりや、シェアリングエコノミーの普及、サーキュラーエコノミーの兆しなどは、自律社会の実現に向けた動きと捉えることができます。

Hiro
そう言われればそうかもしれません。ただ,実感としては私の生まれた時代の社会とそんなに大きく変わっていないようにも思えます。本書では次のようにも書いています。
現在進行中の最適化社会の大転換は,そのポランニーの「大転換」に並ぶほど大きな転換期として位置づけられると感じている。いわば社会OSの入れ替えの時代である。しかし,産業革命に端を発して,凄まじい勢いで工業社会を前進させてきた市場経済を中心とする経済システムや生活価値観の慣性力は大きい。だから,新しい社会のOSのインストールは,従来型のOSと様々な社会システム上の衝突を招いたり,変化のカーブを曲がり切れずに暴走したり,多くの軋轢や混乱,渾沌を生んでいる。しかし,それは当然の出来事なのだ。人々は新旧OSの相克のもとで葛藤し続けている。これらは,最適化の渦中の,避けられない痛みなのだ。(略)
また,これらの最適化の潮流は,一見,情報化社会の延長戦上のようにも見えるが,それは技術的な流れとしての見方であり,社会や産業としては,これまでの常識が常識でなくなるような,破壊的イノベーションが次々に成立している。まさに,非連続的な大転換が起こったと言えるのだ。
その中身といえば,自動制御技術・電子制御技術・生体制御技術・精神生体技術と言われている技術であり,組織が多様性を尊重しながら構成員(従業員)一人ひとりの快適さや幸福を考える形態に変容することである,と本書で述べています。

Hiro
問題2.組織が「個のための組織」「共感ベース」と進化していくとして,現状の資本主義の根幹である「株式制度」との兼ね合いはどうなるのでしょうか,本書ではどう述べているでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。
予 想
ア.「株式制度」はそのまま残っていかざるを得ない
イ.「株式制度」はESG(Environment Social Governance)といわれる環境や社会への配慮,企業統治の向上を通じて企業価値の拡大を目指す投資に変化していく
ウ.その他
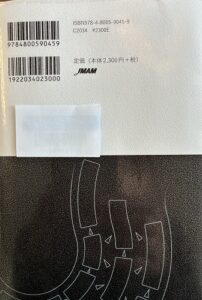

Hiro
正解は,イ.になります。本書では,自律社会の組織とは,利己的ではなく,利他的であると言っています。

Hiro
「株式制度」がどう変化していくのか,私にはわかりませんが,「共感」の浸透によってお金の流れや投資のあり方は大きく変化していくことでしょう。

Hiro
問題3.本書では,人間社会の未来をどうとらえているでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。
予 想
ア.2045年に社会や生活,人間のあり方における特異点がやってくる,つまり,
コンピュータの「知能」が人間の知能を超えて,超知能を獲得する時代がくる
イ.すべてを支配した人間の到達点は,人間を超える唯一の存在である「神」になる
ウ.生態系に人間も,人間の知から生まれるテクノロジーも埋め込まれ,少なくとも意識的な人工物にコントロールされることなく持続する社会になる
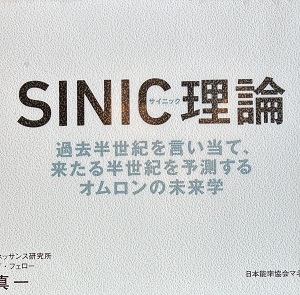

Hiro

Hiro
最後に,新しい社会はどのようにできるのか本書より抜き書きします。
日本では,まだまだ自律社会も到来しないし,最適化社会の渾沌が終息するとは思えないという声が多いのに対し,海外の彼らはほぼ同様に未来シナリオは,もっと時期が早まると思うと語る。こういう議論がオープン・ソースとなったSINIC理論をもとに,世界で行われるようになると,よりよい未来の創造は,もっと価値のあるものとして実現されていく。そして,より価値のあるソーシャルニーズの創造に結びついていくはずだ。(間)
「想像」において,多様なメンバーで未来を想うことが必要だ。それは,年齢や性別,職業だけのことではない。住まいや趣味,関心事やキャリアビジョンなど,様々な観点での多様性を担保したメンバーでの想像が必要だ。その時に大事なのは,その人の未来を生きる当事者としての感覚の確かさである。未来における学生,未来における母親,父親,未来における高齢者,彼らが当事者として想像する未来像からは,新しいソーシャルニーズが見えてくるはずだ。そして,未来の創造にとりかかれる。(略)
たぶん,セカンド・ルネッサンスの主役も同様に,工業社会から生きてきた人間ではなく,情報社会,成熟社会の到来後に生まれた,過去のしがらみも慣性力の影響もない,新世代だろう。

Hiro
本書とは関係ありませんが,私は仮説実験授業
※1を世界に広めようと50歳頃から私なりに努力してきました。しかし,私が望んだように事は進みませんでした。私がやってきたことはブログ「ヒロじいの独り言」
https://tk-s-e-office.comにも載せています。時間があればですが,よかったら読んでみてください。本書を読んでみてオムロンを創業された立石一真氏は,熊本出身だとわかりました。(時代は異なりますが,私も熊本出身です)それに,立石さんは,かなり苦労されていることもわかりました。私と違うところは,立石氏は挑戦され続けてきたということでしょう!立石氏の言葉に「ものごとを“できません”というな。どうすればできるかを工夫してみること」というのがあります。また次のような言葉もあります。「日本もいよいよ先進国の仲間入りをした以上,いままでのように先輩,先進国の手本があって,これを真似してやれば間違いなしにやれたという時代は過ぎた。従来は技術を導入しておれば,なんとかなったが,いよいよ先進国と同じスタートラインに立って欧米諸国と競うのだから,もう手本もない。われわれの創意工夫があるのみである(以下略)」
この言葉は,仮説実験授業研究会元代表の故板倉聖宣の考え方と似ています。板倉は1970年代に中学生の90%以上が高校に入学する時代を迎え,「日本の教育は,大きく変わらなくてはいけない」という内容のことを述べています。また,「日本は模倣の時代が終わり,自分たちで道を見つけなければいけない時代になった」とも言っています。
このSINIC理論は,おそらく人類の未来を切り拓くための新しい指針になるに違いないと感じました。この本に出会えたことをたいへんうれしく思います。
仮説実験授業※1とは(ウキペディアより)
科学上の最も基礎的な概念や原理・原則を教えることを意図した授業である。1963年(昭和38年)に板倉聖宣が科学史研究の成果をふまえて提唱した。仮説実験授業は授業の内容をすべて規定した「授業書」と称するテキストを用い、授業運営法にしたがって授業を進める。仮説実験授業は子どもたちが様々な側面からの問いかけと実験を楽しく繰り返しながら、授業書が目的とする科学的認識に至る経験ができるように作られている。授業書による授業が終わる頃には、ほとんどの子どもたちは自分が獲得した科学的認識を使って、未知の問題の結果を予想できるようになる。

Shige
忙しい毎日,たまには温泉へ行ってのんびりしませんか?
私は,たまーに温泉へ行ってのんびりします。
あなたも,温泉にでもつかってゆっくりしませんか?
私のおすすめは,兵庫県北部にある湯村温泉です。
小さな温泉地でのんびりできると思います。
湯村温泉はこんなところです。
→ https://tk-s-e-office.com/?p=2325
旅館のおすすめは,部屋が広くて,リーズナブルなのはコトブキ(残念ながら露天風呂はありません!),プライベートな空間で食事をして,豪華で大きな露天風呂があるのは朝野家,プールやゲームコーナーがあってリーズナブルなのは井づつや,古い旅館でもいいなら<とみや>(笑)
やっぱり「朝の家」最高!(湯村温泉)
→https://tk-s-e-office.com/?p=2880
このプールいいよね!(兵庫県・湯村温泉)
→https://tk-s-e-office.com/?p=2805
旅館の近くには,<さんそん>という居酒屋があります。日本酒のソムリエがいておいしい日本酒を飲むならココ!
<さんそん>の近くに<中華料理 笑来園(しょうらいえん)>があります。ここは,餃子がおいしいです!
<じゃらん>では,いろんな種類の宿泊施設を紹介しています。
・犬や猫と一緒に泊まれる宿。
・露天風呂付き客室がある宿。
・リーズナブルな宿。
・市内にある交通の便がとてつもなく便利な宿。
一例として,熊本市内で宿泊するなら,熊本駅前すぐにある<THE BLOSSOM KUMAMOTO>ホテルがお勧めです!このホテルのキングサイズベッドの部屋は見晴らしが良くて最高でした!
あなたの宿泊条件にピッタリの宿が必ずあります。
お値段の設定もいろいろです。
ぜひ調べてみてください。
私は,下のサイトから予約しています!
【じゃらん】国内25,000軒の宿をネットで予約OK!2%ポイント還元!