
私の孫であるAちゃんは,小学6年生です。来年から中学生になるということで,科学の一番基本概念である「重さ」の授業をしようと思い立ちました。しかも,私の家で。

仮説実験授業をするには一人では意見の交流ができないと考え,他の孫2人Bくん,Cちゃん(小学3年生と2年生)も一緒に教えることにしました。

それから私の娘Dさん(小学校教諭13年目)も加わってもらいました。彼女には,仮説実験授業の雰囲気だけでも知って欲しかったからです。

子どもといえども,忙しい彼,彼女等です。全員集まれるような日は一日しかないだろうと思い,2024年7月25日(木)に実施することにしました。

後から考えると少し,いや大いに無謀だったと感じています。とは言え,実際に授業をしたことは確かなので,その時の様子をあなたにお伝えできたらと思います。何かの参考にしていただけたら嬉しいです。 最後まで,お付き合いよろしくお願いいたします。

さて,いきなりですが授業が終わっての子ども達+大人の評価及び感想を載せてみます。

あなたは,子ども達のこの授業についての評価はどうだったと思いますか。私は,仮説実験授業が終わるといつも必ず子ども達に授業の評価をしてもらいます。これは,仮説をする場合の決まり事なのです。今回の授業は子ども達にとってどうだったのか,ここで予想してみてください。

子ども達に尋ねた質問は,2つあります。この授業「ものとその重さ」は「楽しかったですか」と,「よくわかりましたか」の2点です。下記の予想から1つずつ選んでみてください。
-
「楽しかったかどうか」についての予想は,
-
「よくわかったかどうか」についての予想は,

私は,ア.すべての人が<楽しかった>を選んだ,
また,ウ.<よくわかった>や<わからなかった>を選んだ,
と予想しました。

実際は次のような結果でした。


予想の結果は,両方ともウが正解でした。

私の予想としては,内容が「わからない」にしても,おそらく全員が「楽しかった」を選ぶだろうと予想していたのですが,大きく外れてしまいました。

その理由を自分なりに考えたのですが,1日で「ものとその重さ」をやってしまったということが一番の原因だったと考えています。

大人の仮説の会では,一日または二日をかけて,ぶっ通しで授業をするのが常です。一日で授業を終えることについて,子ども達には無理があったようです。また,同じような内容の勉強をする時間が長すぎたために嫌になってしまったようです。

しかし,実験を見るときの子ども達の様子を観察すると,とても集中していたように思います。「いやだ,いやだ」と言いながらも,その時は集中してじーっと私の手元(実験結果)を見ていたのが印象的でした。

この授業を通して私が驚いたことが1つありました。それは,次のような質問です。

この質問は難しいみたいで,一般的なクラスの中でも数人しか考えられないのですが,Aちゃんが考えられたことです。Aちゃんは,しっかり説明してくれました。

□1枚では,上皿てんびんで量ることができないので,前の問題でこの用紙1枚が2gだとわかっています。この用紙の縦と横の長さを測ると約21cmと約14cmなので, 21×14は294 この用紙では□が294枚分あることになります。だから□1枚の重さは,
およそ2÷294=0.0068g になります。

もちろん計算もAちゃんが自分でしてくれました。みんなで拍手をしたのは言うまでもありません。
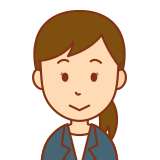
すごいなあ Aちゃん!

わー,すごーい!

本当に素晴らしいと思いました。このことは,Aちゃんにとって大きな自信になったのでないでしょうか。

このことだけでも授業をやってよかったと思いました。

最後に,授業を終えての子ども達の感想を載せてこのレポートを閉じたいと思います。( )の中の番号は,それぞれ楽しかった,わかったかの番号になります。
- おもんなかったし,しょうもない,ながい,いややった,やりたくない。
- なぜおもくなるのかや,まぜたらどうなるかをべんきょうして,頭がとてもよくなったと思いました。またやってみたいと思いました。
- みんなで想像しながらしました。がんばって計算しているAちゃんがすごかったです✨

温泉旅行はどうですか?
私は,たまーに温泉へ行ってのんびりします。
あなたも,温泉にでもつかってゆっくりしませんか?
私のおすすめは,兵庫県北部にある湯村温泉です。
小さな温泉地でのんびりできると思います。
湯村温泉はこんなところです。
→ https://tk-s-e-office.com/?p=2325
旅館のおすすめは,部屋が広くて,リーズナブルなのはコトブキ(残念ながら露天風呂はありません!),プライベートな空間で食事をして,豪華で大きな露天風呂があるのは朝野家,プールやゲームコーナーがあってリーズナブルなのは井づつや,古い旅館でもいいなら<とみや>(笑)
やっぱり「朝の家」最高!(湯村温泉)
→https://tk-s-e-office.com/?p=2880
このプールいいよね!(兵庫県・湯村温泉)
→https://tk-s-e-office.com/?p=2805
旅館の近くには,<さんそん>という居酒屋があります。日本酒のソムリエがいておいしい日本酒を飲むならココ!
<さんそん>の近くに<中華料理 笑来園(しょうらいえん)>があります。ここは,餃子がおいしいです!
<じゃらん>では,いろんな種類の宿泊施設を紹介しています。
・犬や猫と一緒に泊まれる宿。
・露天風呂付き客室がある宿。
・リーズナブルな宿。
・市内にある交通の便がとてつもなく便利な宿。
一例として,熊本市内で宿泊するなら,熊本駅前すぐにある<THE BLOSSOM KUMAMOTO>ホテルがお勧めです!このホテルのキングサイズベッドの部屋は見晴らしが良くて最高でした!
あなたの宿泊条件にピッタリの宿が必ずあります。
お値段の設定もいろいろです。
ぜひ調べてみてください。
私は,下のサイトから予約しています。

